20 光源氏、頭中将と青海波を舞う
物語は「紅葉賀」へ進みます。源氏は18歳か19歳、研究者によって年立(としだて)が若干違うようです。冒頭に「朱雀院の行幸は神無月の十日あまりなり」とあります。朱雀院には桐壷帝の先帝(おそらく父か兄)が住んでおり、祝賀(40歳か50歳の祝い?)に桐壷帝が出かけるのが十月中旬です。その折に光源氏と頭中将が舞うことになっている青海波(せいがいは)の試楽(リハーサル、オペラのゲネプロみたいなものか)が清涼殿で催されます。本番を見られない身重の藤壺女御への帝のはからいです。なんてやさしい夫だろう。
翌朝、源氏は藤壺に歌を贈ります。ちなみに作中で源氏と藤壺は十首の歌のやり取りをしていますが、そのうち八首は源氏が藤壺に贈ったものです。これはそのうちの一つです。
もの思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の 袖うちふりし心知りきや(源氏)
「もの思いのために、とても舞どころではないわたしが、とくにあなたが御覧になる試楽ゆえに、あえて袖を打ち振り舞いました、その心中をお察しくださいましたか。」源氏としては、あなたへの切ない想いに心乱れながら舞ったのですよ、と言いたいのでしょう。これにたいして藤壺は返歌をしています。
から人の袖ふることは遠けれど たちゐにつけてあはれとは見き(藤壺)
「唐土の人が袖を振って舞ったという故事にはうとうございますが、あなたの舞の一挙一動につけて、しみじみ感慨深く拝見しました。」藤壺が「から人(唐人)」と言っているのは、青海波がもともと唐楽を改作した雅楽の曲目だからです。実際には源氏への複雑な感情が渦巻いて、とても無心に見られなかった、というのが本音でしょう。そのことを悲しんでいるようにもとれます。
「遠けれど」というのは、藤壺の目に映った源氏の姿でもあるでしょう。目の前で立ち舞う源氏の姿を「遠い」と感じている。それは心理的な距離感でもあり、厳しい掟に支配された現実の距離感でもあるでしょう。いまをすでに追憶している感じでもあります。あたかも過去の人のように偲んでいる。その後の展開を知っているぼくたちは、藤壺の出家を予言しているようにも感じてしまう。いずれにしても、このあたりが藤壺という女性の独特の心情と感じさせられるところです。
一方、返事をもらった源氏は喜びました。「持経のやうにひきひろげて見ゐたまへり」とあります。尊い法華経のように押し戴き、いつまでも見入っているといったところでしょうか。藤壺にたいする崇拝ぶりがうかがえます。
その藤壺の子は、予定日を過ぎても生まれません。帝も女官たちもやきもきしている。藤壺は出産の遅延をあやしまれて、源氏とのことが露見しないかと恐れ嘆いています。源氏のほうは密会の時期を重ね合わせて「やっぱり」と思っている。年が改まり二月になって、ようやく男の子が生まれます。それまでの心配や疑惑は消し飛び、一同は皇子の誕生を喜びます。
帝は一日も早くわが子を見たいと思いますが、藤壺は「生まれたばかりで見苦しいころですから」などと言ってなかなか見せようとしません。男児があまりにも源氏と似ているので、見せればかならず父親が誰かわかってしまうだろうと心配しているのです。四月になって、若宮は「父」の帝のもとへ移ります。当然、桐壷帝は皇子を溺愛します。遊びにきている源氏に「わが子」を見せる場面です。
「皇子たちあまたあれど、そこをのみなむ、かかるほどより明け暮れ見し。されば思ひわたさるるにやあらむ、いとよくこそおぼえたれ。いと小さきほどは、みなかくのみあるわざにやあらむ」とて、いみじくうつくしと思ひきこえさせたまへり。中将の君、面の色かはる心地して、恐ろしうも、かたじけなくも、うれしくも、あはれにも、かたがたうつろふ心地して、涙落ちぬべし。(「紅葉賀」)
帝は無邪気に「いとよくこそおぼえたれ」などと言っています。「皇子たちはたくさんいるけれど、そなた(源氏のこと)だけを幼いころから明け暮れにそばにおいて見ていたものだ。それで自然とそのころのことが思い出されるのだろうか、この子はまことにそなたによく似ている。ごく小さいうちは、みんなこんなものなのかねえ」と、まったく疑う様子もありません。それを聞いて源氏は青くなる。
実の父にそんなことを言われては、源氏としては涙をこぼすしかなかったのでしょう。それにしても桐壷帝は本当に真相を知らなかったのでしょうか。あるいはうすうす感づいていて鎌をかけているのでしょうか。光源氏ならずとも、「かたがたうつろふ心地」する場面ではあります。
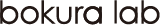

 Twitter
Twitter