22 「限りあれば」という世界観
今回は『源氏物語』のなかに頻出する「限り」という言葉について考えてみましょう。「限り」には限界とか範囲とか期間とか、いろいろな意味がありますが、ここでは決まり、規則、掟といった意味で見ていきたいと思います。
たとえば「葵」の帖では、亡くなった葵の上を悼んで源氏が歌を詠みます。
限りあれば薄墨ごろもあさけれど 涙ぞそでをふちとなしける
この場合は喪服についての規則ですね。妻の喪は軽服(きょうぶく)で薄墨色と定められていました。「服」は衣服の服ではなくて、喪に服すのほうでしょう。軽い喪、遠縁の者の死ということになるでしょう。正妻が「遠い縁」というのは、ちょっと頷けない感じですね。これにたいして父母や夫は重服(じゅぶく)で濃い色を用いる。きまりによって薄墨色の喪服しか着られないけれど、深い悲しみの涙が袖口を深い色にしてしまうことでしょう。「ふち」は「淵」と「藤」に掛かります。
「桐壺」の巻では、健康を損ねた更衣が養生のために里へ下がろうとするのを、帝はなかなか認めません。当時のしきたりとして、天皇以外は(たとえ后妃であっても)宮中で死ぬことは禁忌なので、更衣が宮中に留め置かれて亡くなることは許されない。そこで帝も泣く泣く退出を許すことになります。
限りあれば、さのみもえ止めさせたまはず、御覧じだに送らぬおぼつかなさを、言ふ方もなく思ほさる。いとにほひやかに、うつくしげなる人の、いたう面痩せて、いとあはれともの思ひしみながら、言に出でても、聞こえやらず、あるかなきなに消え入りつつ、ものしたまふを、御覧ずるに、来し方行く末思しめされず、よろづのことを、泣く泣く契りのたまはすれど、御答へも聞こえたまはず。まみなどもいとたゆげにて、いとどなよなよと、われかの気色にて伏したれば、いかさまにと
思しめしまどはる。(「桐壺」)
掟のあることだから、帝はそうそうもお引き留めになれず、ご自分がお見送りもあそばされぬ(「御覧じ送る」=見送る)心もとなさを、いいようもなく悲しくおぼしめす。じつにつやつやと美しくてかわいらしく見える方が、すっかり面やつれして、まことにしみじみと世の悲しみを感じていながら、言葉に表してそれを申し上げることもせず、人心地もなくうつらうつらしていらっしゃるのをご覧になると、帝は、あとさきのご分別もおなくしになって、あらんかぎりのことを泣く泣くお約束あそばすけれども、更衣はお返事を申し上げることもおできにならない。まなざしなども、ひどくだるそうにしてふだんよりもいっそうなよなよと、正体もない有様(「われか」は「我か人か」の略)で横たわっているから、帝はどうしたものかと途方に暮れておいでになる。
ここでは「限り」が掟の意味で使われています。掟の中身は、宮中に死穢をもたらすことの禁忌(タブー)です。つまり宮中という聖域にたいする禁忌で、現在でも格式ある寺社や霊場、修験の場などは結界や神域とされて、唾をしてはいけないとか、大小便の禁止とか、さまざまな禁忌があります。女人禁制というのも、産褥、出血を嫌うということでしょう。
こうした禁忌が、『源氏物語』のなかにはたくさん出てきます。その一つに「物忌み」というのがあります。異変や凶兆、死穢などの日には、物事を慎み、身を清めて家に籠っていなければならないというもので、陰陽道からきているようです。有名な「雨世の品定め」(「帚木」)では、物忌みで宮中に留め置かれた光源氏、頭中将、左馬頭、藤式部丞の四人がそれぞれの女性体験を語ります(光源氏は体験がないので、もっぱら聞き役)。
同じ「帚木」には「方塞(かたふたがり)」というのも出てきます。これも陰陽道で不吉とされる方向を避けるものです。移動が避けられない場合は、「方違え」といって、前もって別方向に宿るようにしました。光源氏が空蝉を見出すのは、方違えで訪れた紀伊守の邸でのことです。以上見てきたものは、空間的な禁忌と言えるでしょうか。
一方、「限りある命」といえば時間的な意味合いになります。「喪中」というのも時間的な拘束です。さらに「家柄」や「身分」といった制度的なものもあります。位階でいうと、三位以上が公卿とか上達部とか呼ばれ、上流層をなします。四位、五位が、いわゆる「中の品」で中流層です。貴族というのは五位以上です。六位以下は下流層ということになります。こうした位階(階級)によって、結婚も出世(昇進速度)もきまりました。律令制のもとでは、元服して成人と認められると位階を与えられます。それは父親の階級、生まれによって自動的に決まってしまうのです。
夕霧が元服したとき、光源氏は息子にたいして厳しい教育方針をとります。夕霧の場合、父親の権勢からして四位相当のところを、源氏はあえて六位にします。そのため夕霧を可愛がっていた大宮(故葵の上の母親で、夕霧の祖母にあたる)などは、孫が六位の浅葱姿で戻ってきたので、たいへん不満に、また心外に思う(「少女」)。源氏としては親の七光りと思われたくないということしょうが、このあたりの夕霧の処遇には、作者自身の鬱屈した気持ちが反映しているのかもしれません。
というのも、紫式部の父親は藤原為時という人で、受領階級に属していました。受領というのは地方官僚で、いまでいうと県知事みたいなものですしょうか。四位、五位とまりの下級貴族が任にあてられたということです。つまり彼女自身がいわゆる「中の品」の子女だった。いくら頭が良くても、いくら努力しても、皇族や大臣を父にもつ「上の品」の娘たちには勝てない。『紫式部日記』などを読むと、そうした「限り」を超えられない宿命を、彼女自身が非常に鋭敏に感じていたことがわかります。
このように女性の場合も、家系や家柄といった出自に強く規定されていました。「更衣」は天皇の夫人を意味しますが、同時に大納言以下の家の娘という生まれもあらわしています。桐壺が更衣と呼ばれるのは、彼女の亡くなった父親が大納言だったからです。「女御」も更衣と同様に、天皇の夫人を意味しますが、家柄のほうは皇族および摂政、関白、大臣の家の娘ということになっていて、当然、身分は更衣よりも上です。藤壺が女御と呼ばれるのは、先帝の四女(四の宮)で皇族だったからです。ちなみに桐壺更衣は亡くなったあと「御息所」と呼ばれますが、これは天皇に寵愛された女性、とくに皇子、皇女を産んだ女御、更衣の尊称です。
天皇の正妻は「北の方」と呼ばれます。寝殿造りで「北の対」に住んでいたからで、藤壺も文中では「北の対」と呼ばれることがあります。女性にとって正妻か妾(さい、をむな)かは、とても重要な意味をもちました。もちろん子どもにとっても、嫡子か庶子かで、その後の人生は大きく違ってくる。同じ正妻の子でも第一子か第二子以下か。そうした細かな決まり、規則が人々を厳しく拘束していました。
とりわけ『源氏物語』で重要な意味をもつ「限り」は出家です。いわば自分自身を禁忌(タブー)にしてしまうわけですね。これについては藤壺の出家をめぐって、あらためて考えることにして、いまは物語を先に進めましょう。
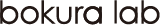

 Twitter
Twitter