19 光源氏、末摘花に寄り道する
身も蓋もない言い方をすれば、平安時代の文学の主題は四季(季節の移り変わり)と性愛、ほぼ二つに尽きています。こうした傾向は、最初の勅撰である『古今和歌集』にとくに著しいように思います。収録されている歌の半分は四季を、残り半分は恋を題材としたものです。お隣の中国の漢詩が政治、思想、哲学、宗教など幅広いテーマを扱っていることからすると、ちょっと異様でもあります。日本人は昔から色ボケしていたのか? 勅撰は天皇の命によって編纂されたものですから、四季と性愛は、平安時代の日本の国是であったという見方もできます。
しののめのほがらほがらと明けゆけば 己が衣々なるぞかなしき(『古今和歌集』恋歌三・よみ人しらず)
褥にいるあいだは二枚重ねて覆っていた衣を、明け方になってそれぞれの身にまとうのが悲しい。そこから「きぬぎぬ」に「後朝」の字を当てて、男女が共寝をした迎えた朝という意味になりました。こんな色っぽい歌を、ときの天皇(醍醐天皇)は「良し」としたわけです。それで国が治まっていたというのはめでたいような、不幸なような。
この後朝が「末摘花」ではとんだ結末に終わります。源氏は亡くなった夕顔のことを未練がましく想いつづけています。葵の上も六条の御息所も、気位が高くてちょっと堅苦しい。もっと気安く付き合える女はいないかなあ、などと虫のいいことを考えています。そこへ大輔命婦のから、常陸宮の箱入り娘が父亡きあと琴などを弾いて寂しく暮らしている、という情報が入ります。心が動いた源氏は命婦の手引きで何度か邸を訪れます。
命婦が言うには、姫君の器量や人柄などはよくわからない。とりあえず手紙を送ってみるけれど返事はない。当然、源氏は「いったいどういう娘なんだ」と腹を立てます。命婦は「とにかく内気ではにかんでばかりいらっしゃるので」などとなだめます。仲人口という言葉があります。仲人が縁談をまとめるために、双方に相手のことを取り繕ってよく言うことだそうです。このときの命婦の姫君についての言は、その仲人口だったようですね。なんとか契りを結んだものの、源氏のなかでは「あれ?」という感じだったのでしょう。
何ごとにつけてかは御心のとまらむ、うちうめかれて、夜深う出でたまひぬ。(「末摘花」)
「夜深う出でたまひぬ」とありますね。まだ夜が明けぬ前に起き出して帰ったということは、要するに失望したのでしょう。先の『古今和歌集』の歌のように「己が衣々なるぞかなしき」とはいかなかったようです。逢瀬のあとには「後朝の文」を送るのが習わしです。この手紙によって相手の気持ちを推し量るわけです。早く来るのは相手の想いが強い証拠。源氏は夕方になって後朝の文を送りますが、「今夜は雨が降って気がめいってしまうなあ」と熱意のなさを示して余りある文面です。
姫君の返信が、またよろしくない。歌の書かれた紙は古びているし、筆遣いも無骨で書体は古く、書き方にも女性らしい心配りがない。源氏はすっかり幻滅してしまいます。それでも彼は義理堅い男なので、姫君のところへ通いつづけます。ある夜明け、源氏は雪明りの助けを借りて女の顔を見てしまう。これがとんでもない醜女だった、というのが話の落ちです。
このときまで女の顔が見えなかったというのは、現代の感覚からするとちょっと考えにくいですよね。それほど貴人たちにしても、夜の暮らしは暗かったということなのでしょう。月でも出ていなければ、逢瀬はほとんど漆黒の闇のなかで営まれることになります。ここから肌を密着していても顔は見えない、という不思議な状況が生まれるわけです。
それにしても姫君(末摘花)の容姿の醜さを描写する紫式部の言葉は、読んでいてあまり気持ちのいいものではありません。ユーモアよりも悪意と容赦のなさが勝っている気がします。これでもかというくらい、一人の女性を貶めることに情熱を傾けている。むしろ書いている作者のほうが偏執的で異常ではないかと思えるくらいです。
控えめに言っても、紫式部の書きぶりには残酷ないじめに近いものが感じられます。女性の読者のなかに、どうしても『源氏物語』は好きになれないという人が少なからずおられるのは、こういうところにも一因があるのかもしれません。ただ、光源氏の振る舞いには余裕があって、「今回ばかりは失敗しちゃった」という感じです。恋敵の頭中将に知られたら馬鹿にされるだろうなあ、などと思い煩っていて、なんとなく好感がもてます。
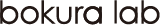

 Twitter
Twitter