21 「前の世」について考えてみる
『源氏物語』の最初の帖で、桐壺帝が他の女御更衣たちを差し置いて、桐壺更衣だけを寵愛するものだから、身分も後ろ盾もない彼女はいろんないやがらせをされ、心労が募って衰弱死してしまいます。自分の振る舞いが最愛の人を死に追いやったようなものなのに、桐壺帝にはそれにたいする反省というか、後悔がまったくありません。ただ「前の世の定め」ということで済ませている。
更衣が死んだあと、帝は残された母親を命婦に見舞わせます。その命婦が帝の気持ちを伝えるところがあります。
「わが御心ながら、あながちに人目驚くばかり思されしも、長かるまじきなりけりと、今はつらかりける人の契りになん。世に、いささかも人の心をまげたることあらじと思ふを、ただこの人のゆゑにて、あまたさるまじき人の恨みを負ひしはてはては、かううち棄てられて、心をさめむ方なきに、いとど人わろうかたくなになりはつるも、前の世ゆかしうなむ。」(「桐壺」)
「自分の心ながら、むやみと、人が見て驚くほどに愛しく思ったのも、思えば長くつづくはずのなかった仲なのだなと、いまとなっては切なく思われる因縁である。
自分ではほんのわずかでも人の気持ちを害したことはあるまいと思っているが、ただこの人のために、多くの受けずともよい人の恨みを買ったその挙句の果てに、このように一人取り残されて、心を鎮める術もないので、ますます人聞きの悪い偏屈ものになってしまったのも、前世の因縁であろうが、それがどんなものだったのかぜひ知りたいものだ。」
ここで桐壺帝は、「前の世」ですでに長くはつづかない契りだと定められていたからこそ、自分は周囲の思惑など顧みる余裕もなく、かくもひたすら更衣を寵愛するはめになったのだと言っています。更衣を死に追い込んでもなお寵愛せずにはおられない帝の内的な事情は、まったく描かれていません。ただ「前の世」からの約束だから仕方がなかったのだ、と考えているふしがある。言い訳しているのでもなければ、自分を慰めているわけでもなく、本心からそう信じているのでしょう。
桐壺帝にかぎらず、『源氏物語』には「前の世」とか「宿世」といった言葉がよく出てきます。先にも見たように、源氏と藤壺が密会して懐妊した事情を知っている命婦の心情を、作者・紫式部は「なほのがれがたりける御宿世をぞ、命婦はあさましと思ふ」と書いています。『源氏物語』という作品全体に「前の世」とか「宿世」といった観念が通底していると言ってもいいでしょう。
更衣の死後、帝が藤壺を入内させるのも、彼女がまるで生き写しのように亡くなった更衣によく似ていると聞いたからですし、光源氏が藤壺を慕うようになるきっかけも、まわりから「亡くなった母上にそっくりですよ」と言われたからです。いずれもたんに類似ということではなくて、輪廻による生まれ変わりという観念を含んでいるように思われます。つまり生まれ変わりの理念にかなっていることが、寵愛や思慕の根拠になっているわけです。
これは近代文学ではちょっと考えられないことです。たとえば夏目漱石の『それから』では、父親からの援助で何不自由なく暮らしていた代助が、破局を予想しながら、友人の奥さんである美千代との関係につき進んで行きます。その心の揺れ動きが、読者にわかるように書かれています。あるいはドストエフスキーの『罪と罰』にしても、貧しい娼婦であるソーニャが、親しい友だちを殺した犯人であるラスコーリニコフを責め立てることもなく、自首を勧めたうえ、シベリアに送られる彼に付き従うのですが、彼女の内的な動機が、暗示的にではあれ、読者に伝わるようになっています。
ところが『源氏物語』では、個人の心情とか内的な動機みたいなものが、ほとんど描かれていない。描かれていても、それは「前の世の定め」や「宿世」といった、より強い力によって押し切られてしまう。登場人物を衝き動かしている力は、その人個人のなかではなく、時間を超えた約束や定めのほうにある。このあたりが物語を跳梁する物の怪などとともに、『源氏物語』という作品がとどめている古代性と言えるかもしれません。
しかし、この古代的と感じられるところが、作品の大きな魅力にもなっている気がします。登場人物は個人的な動機や心情というよりは、「前の世」や「宿世」といった、過去と現在と未来を貫く目に見えない力に導かれて生きている。光源氏の藤壺女御にたいする恋慕も、紫の上にたいする執着も、前の世からの定めによって、あらかじめきめられている。
だから本人の意思ではどうにもならないところが出てきます。その行動はしばしば強引ですし、見方によっては幼児的とも言えます。桐壺帝がまわりの状況も考えずに更衣を寵愛したこと、光源氏が藤壺との闇の恋に入り込んで不義の子をなしたこと、さらに若紫を略奪同然に引き取って理想の女性に育てようとしたこと。いずれも個人の力ではどうすることもできない不可避の振る舞いだった。そういう強い理念によって物語が制御されている印象を受けます。
ぼくたちだってそういうことはある気がします。先の代助にしても、どうして親に勘当されてまで友だちの奥さんを奪うのか。本人にもうまく説明できないかもしれない。本気で人を好きになることは、かならずそうしたニュアンスを含みもつのかもしれない。どうしてこの人を好きになってしまったのか。自分でも理路整然と説明できない。そんなときぼくたちは、偶然を超えた必然みたいなところに引き寄せられるのではないでしょうか。前の世の定めとは言わないまでも、「運命」くらいの言葉は使いかねない気がします。「こうして出会ったのは運命なんだよ」とか。あまり安易にいろんなところで使うと問題ですけど。
親子の場合を考えると、もっとはっきりするかもしれません。ぼくは二人の子どもに恵まれましたが、彼らとの出会いが偶然だったとは思えない。この子たち以外には考えられない。この子たちと出会うために自分は生まれてきた……謙虚で清らかな心境のときには、そんな気持ちになったりします。自分の両親についてもそうです。この両親のもとに生まれてきたのは偶然ではない、この人たち以外には考えられない。意識することはないけれど、無意識にはそう考えていて、それが親子の絆になっているんじゃないでしょうか。こんなふうに考えていくと、ぼくたちのなかにも『源氏物語』を貫いている古代性みたいなのものが、かなり色濃く残っているのかもしれません。
ここで『源氏物語』のなかで「前の世の定め」とか「宿世」とかいわれているものを、時間の垂直性と言い換えてみたい気がします。光源氏が藤壺を恋慕するのは、たんに亡くなった母親の代償を求めているのではなく、藤壺のなかに桐壺更衣が追憶されているはずです。同様に若紫のなかには、藤壺が追憶されている。それは光源氏のなかを垂直に流れる時間と言ってもいいように思います。
ぼくたちのなかを垂直に流れている時間、過去と現在と未来を貫いて流れている垂直の時間。それは人間の心情の奥深いところにある、かなり本質的なものではないでしょうか。人を人として駆動させた情動に近いものなのかもしれない。そんなふうに考えていくと、『源氏物語』に通底している古代性を、「未来性」というところまでもっていくことができる気がします。
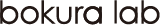

 Twitter
Twitter