23 光源氏、朧月夜と出会う
ようやく第八帖、「花宴」です。物語は旧暦の二月の末、紫宸殿での桜の宴のシーンからはじまります。紫宸殿というのは内裏の正殿で、即位や朝賀など、宮廷の重要な儀式が執り行われるところです。藤壺以下、正妻である弘徽殿女御、息子の春宮(のちの朱雀帝)などが勢揃いしている。ここでも源氏はすぐれた詩才を示します。宴会だからお酒をたしなまれたのでしょう。酔っぱらった源氏は藤壺のあたりをうかがい歩きますが、ガードが固くて忍び込めない。しょうがないので、戸口が開いていた弘徽殿の細殿(廂の間)に潜り込みます。まったく二十歳になっても不良ぶりはつづいているってとこですね。
女たちは寝静まっているようです。藤壺と違って弘徽殿は戸締りがルーズだったらしく、若者はどんどん奥へ進んでいきます。すると若い女の声で「朧月夜に似るものぞなし」(「照りもせず曇りも果てぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」という大江千里の歌を言い換えたもの)を口ずさむ者がいる。女房や召使たちではなさそうだ。源氏は「やったァ」と思って、女の袖をむんずとつかんだ……。
女、恐ろしと思へる気色にて、「あなむくつけ。こは誰そ」とのたまへど、「何かうとましき」とて、「深き夜のあはれを知るも入る月のおぼろけならぬ契りとぞ
思ふ」とて、やをら抱き降ろして、戸は押し立てつ。あさましきにあきれたるさま、いとなつかしうをかしげなり。わななくわななく、「ここに、人」とのたまへど
、「まろは、皆人にゆるされたれば、召し寄せたりとも、なむでふことかあらん。ただ忍びてこそ」とのたまふ声に、この君なりけり、と聞き定めて、いささか慰め
けり。(「花宴」)
「むくつけき」は連体詞として現代でも使いますね。粗野でむさくるしい。古語の意味もだいたい同じで、気味が悪い。これにたいして源氏は、「何が怖いものですか。あなたが月の風情に感じ入られたのも、わたしと出会う並々ならぬ縁ゆかりがあったからでしょう」と、都合のいいことを言っています。そのまま女を細殿に抱き降ろして戸を閉めてしまいました。女はあまりのことに呆れはてていますが、その様子が人なつこく、愛くるしい(「いとなつかしうをかしげなり」)。
女は怖さに震えながら、「ここに人が」と声を上げる。「わたしは誰からも許されているのですから、人を呼んでもなんにもなりませんよ。どうぞお静かに」という源氏の台詞は、自信満々で憎たらしいほどです。その声を聞いて相手が源氏であることがわかり、少し安心したというのだから、どっちもどっちというところでしょうか。
この女性、作中では朧月夜と呼ばれていますが、じつは源氏を憎んでいる弘徽殿の女御(桐壷帝の正妻)の父・右大臣の六女で、四月には東宮(のちの朱雀帝)に入内がきまっています。源氏はそのことを知らずに密会をつづけます。とうとう現場を押さえられ、激怒した弘徽殿女御の圧力によって須磨に蟄居せざるをえない事態に追い込まれます。
その前に「紅葉賀」で書き落したことに触れておきます。巻の最後のところで、藤壺が中宮になったことが語られます。第一夫人の弘徽殿としては当然面白くない。それを桐壺帝は「春宮の御世、いと近うなりぬれば、疑ひなき御位なり。思ほしのどめよ」と言って宥めます。帝と弘徽殿の子である春宮が帝として即位する日も近い。そのときはあなたも皇后になるわけだから、まあ焦らずに待っていなさい、ということですが、これは藤壺との子(と帝自身は思っているけれど、じつは源氏との不義の子)を東宮(春宮)にするための配慮と考えられます。母親(藤壺)を中宮にしておけば、弘徽殿を母とする一の宮が帝になったときに、藤壺との子(若宮)は東宮に就きやすくなる。
もともと中宮と皇后は同じ意味です。東宮(春宮)と同様、皇后の住む場所を中宮と呼んだわけです。ところが権勢をほこる藤原道長が、皇后と中宮を分離させて、一条天皇の中宮であった兄・道隆の娘・定子を皇后に、自分の娘・彰子を女御から無理やり中宮にしてしまった。このように一人の天皇に同時期に二人の后(皇后・中宮)を立てることは異例で、「一帝二后冊立」などと呼ばれますが、ここでの桐壺帝の措置は、そうした歴史的事実を踏まえているのかもしれません。
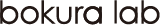

 Twitter
Twitter