24 桐壺帝、光源氏に説教をする
さて、巻は進んで「葵」です。「花宴」から2年、源氏は22歳になっています。官位も近衛中将から大将に進んでいる。すでに桐壷帝は退位し、息子の朱雀帝(光源氏の兄)が即位しています。藤壺の産んだ皇子(のちの冷泉帝)は東宮になっており、後見は実の父である光源氏です。桐壷院は御所で藤壺と気楽な隠居生活を楽しんでおり、ますます近づくことができない。
そのころ六条に御息所の娘が伊勢の斎宮にきまります。斎宮というのは伊勢神宮に奉仕する未婚の皇女または女王で、きまると潔斎に入り、3年経つと伊勢に行くことになります。六条御息所は源氏の愛情が薄いことを自覚して、娘と一緒に伊勢に行こうかなどと思っています。
桐壷院はそうした事情を聞き知って、息子にお説教をします。
「故宮のいとやむごとなく思し、時めかしたまひしものを、軽々しうおしなべたるさまにもてなすなるがいとほしきこと。斎宮をもこの皇女たちの列になむ思へば、いづ方につけてもおろかならざらむこそよからめ。心のすさびにまかせて、かくすきわざするは、いと世のもどき負ひぬべきことなり」など、御気色あしければ、わが御心地にもげにと思ひ知らるれば、かしこまりてさぶらひたまふ。(「葵」)
「御息所は亡き東宮が大切に思われた方なのに、おまえは軽々しく並々の人のように扱っているそうではないか。斎宮(御息所の娘)のことも、わたしは自分の娘と同列に思っている。あまり誠意のないことはしないほうがいい。勝手気ままに浮気を繰り返していると、世間の非難を浴びることになるぞ」と機嫌が悪い。源氏のほうでも、なるほど仰せのとおりだと恐縮して聞いている。
実際に、父親からこんなことを言われるとどういう気持ちがするものなんでしょう? まして藤壺とのことがあるわけですからね。もし発覚すれば、という恐れは、当然あったはずです。まさに身も心も縮む思いで話を聞いていたことでしょう。
さらに院は、「いづれをもなだらかにもてなして、女の怨みな負ひそ」と付け加えます。どちらもみな角の立たないように扱って、女の怨みを買ってはならない。
つまり全部の女を公平に可愛がれということで、いまどきのまともな父親なら言いそうにないことですが、天子は多くの女性たちの呪力によって国を治めたという、古代の習俗がなおこの時代には生きていたのかもしれません。
そういうお説教をする人が、じつは説教を垂れている相手の男(息子)に奥さんを寝取られているという筋書きは、考えてみるとかなり意地悪ですね。ヨーロッパの近代小説などにもありそうです。紫式部の毒を含んだ皮肉は、男全般に向けられているのかもしれません。ここでの帝のお説教は、あとにつづく御息所と葵の上の確執のプロローグにもなっています。
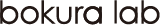

 Twitter
Twitter