25 葵の上、懐妊する
源氏の正妻である葵の上が妊娠します。ときを同じくして、新しい斎院(賀茂神社に奉仕する未婚の皇女または女王)がきまり、賀茂の河原で禊が執り行われることになる。この神事の行列には源氏も加わるので、妊娠中の葵の上は女房たちにせがまれて見物に出かけます。六条御息所もまた恋人の晴れ姿を一目見たいという思いを抑えきれず、人目を避けて網代車で出かける。一条大路の雑踏のなかで葵の上が乗った左大臣家の車と、六条御息所の車のあいだに車争いの不祥事が起こります。
そんなことがあってから、御息所はもの思いに心乱れる日々を送っています。一方、左大臣家では懐妊中の葵の上が物の怪に苦しめられている。
大殿には、御物の怪いたう起こりていみじうわづらひたまふ。この御生霊、故父大臣の御霊など言ふものありと聞きたまふにつけて、思しつづくれば、身ひとつのうき嘆きよりほかに人をあしかれなどと思ふ心もなけれど、もの思ひにあくがるなる魂は、さもやあらむと思し知らるることもあり。(「葵」)
この箇所は瀬戸内寂聴訳では以下のようになっています。〈左大臣家では、葵の上に物の怪がさかんに現れて、その度、御病人はたいそうお苦しみになります。六条御息所は、それを御自身の生霊とか、亡き父大臣の死霊などと、噂している者があるとお聞きになるにつけて、あれこれと考えつづけてごらんになります。いつでも自分ひとりの不幸を嘆くばかりで、それよりほかに他人の身の上を悪くなれなど、呪う心はさらさらなかった。けれども人はあまり悩みつづけると自分で知らない間に、魂が体から抜け出してさ迷い離れていくといわれているから、もしかしたら自分にもそういうこともあて、あの方にとり憑いていたのかもしれないと、思い当たる節もあるのでした。〉
訳文のなかで「いつでも自分ひとりの……」以下のところは、六条御息所の心のなかをそのまま描写する書き方になっています。あたかも語り手が、登場人物の心のなかを覗き込んでいるかのようです。
ちなみに瀬戸内訳よりも古い与謝野晶子の訳ではつぎのようになっています。〈葵の君の容体はますます悪い。六条御息所の生霊であるとも、その父である故人の大臣の亡霊が憑いている言われる噂の聞こえて来た時、御息所は自分自身の薄命を歎くほかに人を詛う心などはないが、物思いがつのればからだから離れることのあるという魂はあるいはそんな恨みを告に源氏の夫人の病床へ出没するのかもしれないと、こんなふうに悟られることもあるのであった。〉
瀬戸内訳にくらべると素っ気ないくらいすっきりしているけれど、そのぶんニュートラルな場所からなされる御息所の心情描写が際立っています。
ここで物語を語っているのは誰でしょう? 何者と考えればいいのでしょう? とりあえず作者は、源氏の近くにいる女房が宮中内の出来事を語る、という書き方をしています。紫式部自身が、夫を亡くしたあと藤原道長の娘(中宮彰子)に仕えていますから、自分に近い語り手を設定したのでしょう。『紫式部日記』を見ると、作者は彰子の出産に立ち会っています。当然、そのときの見聞が作品に取り入れられているはずです。しかし語り手は、出来事を外側から記述するだけでなく、登場人物の心のなかに入り込み、さりげなく心情を描写します。
こうした手法は、ヨーロッパの文学では近代に至るまで見られなかったものです。いわゆる「三人称客観描写」と呼ばれる叙述のスタイルで、通説ではフローベールが『感情教育』で確立したとされます。これ以降、語り手は物語のなかに姿を見せないことが一つの理想とされるようになりました。語り手は、透明であるがゆえに、登場人物の心のなかにするりと入り込んで、その思考や感情を記述することができるわけです。
七月のはじめの酷暑のころのある日の夕暮れ近く、一人の青年が、小部屋を借りているS横町のある建物の門をふらりと出て、思いまようらしく、のろのろと、K橋のほうへ歩きだした。彼は運よく階段のところでおかみに会わずにすんだ。彼の小部屋は高い五階建ての建物の屋根裏にあって、部屋というよりは、納戸に近かった。賄いと女中つきでこの小部屋を彼に貸していたおかみの部屋は、一階下にあって、彼の小部屋とははなれていたが、外に出ようと思えば、たいていは階段に向い開けはなしになっているおかみの台所のまえを、どうしても通らなければならなかった。そして青年はその台所のまえを通るたびに、なんとなく重苦しい気おくれを感じて、そんな自分の気持が恥ずかしくなり、顔をしかめるのだった。借りがたまっていて、おかみに会うのがこわかったのである。(ドストエフスキー『罪と罰』工藤精一郎訳)
ここでは三人称の客観的な描写が、いつのまにか主人公の内面描写(「なんとなく重苦しい気おくれを感じて……」)になっています。語り手が登場人物について叙述しているところと、その人物の心のなかに入り込んで直接的に彼の心理を叙述しているところを、スムースにつなぐことができています。近代以降の小説の大きな特徴の一つと言っていいでしょう。文学史的には、19世紀のヨーロッパでさかんに試みられるようになる手法ですが、それを1000年も前の日本の女性がやっていたというのは、なんだか不思議な気がします。
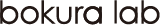

 Twitter
Twitter