26 物の怪、葵の上に取り憑く
「葵」の巻では、葵の上と六条御息所という名門に生まれた二人の誇り高い女たちの情念が、源氏という一人の男をめぐってぶつかり合います。『源氏物語』のなかでも、とりわけドラマチックな場面を含んでいるのですが、その緊迫感は源氏が物の怪の正体を知ることで一気に高まります。
まださるべきほどにもあらず、と皆人もたゆみたまへるに、にはかに御気色ありて悩みたまへば、いとどしき御祈祷数を尽くしてさせたまへれど、例の執念き御物の怪ひとつさらに動かず。やむごとなき験者ども、めづらかなりともてなやむ。さすがにいみじう調ぜられて、心苦しげに泣きわびて、「すこしゆるべたまへや。大将に聞こゆるべきことあり」とのたまふ。(「葵」)
出産を控えた葵の上が、物の怪に取り憑かれて苦しんでいます。いろいろ修法や祈祷をやってみると、物の怪や生霊のようなものがたくさん出てきた。ところが一つだけ、しつこく取り憑いて離れない物の怪がある。上の容体は悪くなる一方だ。源氏が見舞うと、彼女に取り憑いている物の怪が、「苦しくてしょうがないから調伏を緩めてくれ。大将(源氏)に申し上げることがある」と訴える。
源氏はあくまで自分の妻(葵の上)だと思って看病しています。その回復が思わしくない。ひょっとすると死別もありうる。そんな相手の胸中を推し量って、「夫婦の縁は二世にわたるというから、きっとまたお目にかかれるでしょう」などと慰めている。ところが目の前の葵の上は、ここではっきり六条御息所の生霊として発言しはじめます。
「いで、あらずや。身の上のいと苦しきを、しばしやすめたまへと聞こえむとてなむ。かく参り来むともさらに思はぬを、もの思ふ人の魂はげにあくがるるものになむありける」となつかしげに言ひて、「なげきわび空に乱るるわが魂を結びとどめよしかがひのつま」とのたまふ声、けはひ、その人にもあらず変りためへり。いとあやしと思しめぐらすに、ただかの御息所なりけり。(「葵」)
「いや、そうではないのです。わたし自身が苦しくてたまらないので、しばらく加持をやめていただきたいのです。こんふうに参上するつもりはなかったのに、もの思いをする者の魂は、身を離れてさまよい出るもののようです」と懐かしそうに言って、「嘆きに嘆いてわが身を離れて宙を迷っている魂を、どうかつなぎとめておいてください」という歌を口にする。嘆願しているのは葵の上なのだが、その声も顔も六条御息所にそっくりになっていく。
物の怪の話は、『栄花物語』や『大鏡』といった歴史物語にも出てきます。もちろん当時の人々が物の怪の存在を信じて疑わなかった、ということがあります。それは「前の世」や「宿世」といった、輪廻や因果応報の世界観が信じられていたこととも関連するでしょう。一方で、この時代の物の怪や悪霊の多くが、「外戚政治」という特殊な権力構造によって生み出されていることにも注目したいと思います。娘を入内させて次代の天皇を産ませる、自らは外戚となって権力を握る。そうした野望が渦巻く狭い空間で、夢破れた父娘の憎悪や怨念を、本人たちだけでなく、まわりも強く感受せざるを得なかったのでしょう。栄華の極みに立った道長自身が、晩年は物の怪に悩まされたといいます。
その点、『源氏物語』の物の怪は少し違います。先に見た夕顔を取り殺す物の怪にしても、ここで葵の上に憑いている物の怪もしても、男女のエロスがからんでいます。この場面でも、物の怪を六条御息所の生霊と認識しているのは光源氏だけです。つまり現れた物の怪は、二人のもつれた愛人関係を象徴しているとも言える。
このあたりが『源氏物語』の非常に優れたところだし、またモダンに見えるところです。「小説的」と言ってもいいかもしれません。当時は「小説」というスタイルはなくて、主人公の誕生から語り起こすとか、比較的短いエピソードを集めた説話的な構成をとっているとか、『源氏物語』も一応は古代物語や神話の系譜上にあるわけですが、作者の冴えというか、才気煥発な筆が、そうした古代性を乗り越えていくのですね。
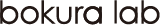

 Twitter
Twitter